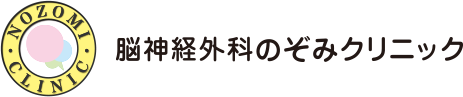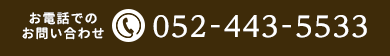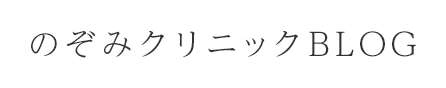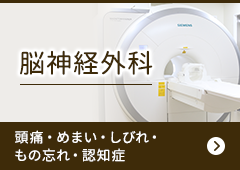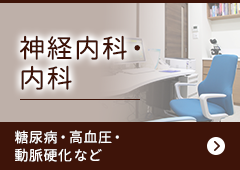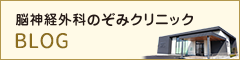相変わらず米の高騰が続いてますね。
政府が備蓄米を放出して価格を下げようとしたようですがあまり効果はありませんでしたね。そりゃーそうだと思いますよ。例えば年に5回興行するアイドル歌手のディナーショーがあったとして、それが10万円で完売したとしますでしょ。これを年10回に増やしたら供給量が上がるから値段が下がるかっちゅー話です。ちょっとばかり回数が増えたとしても、10万円で完売するなら10万円で売りますよね。価格の決め手はアイドル歌手の人気…すなわちニーズなので、例え毎日ディナーショーをやったってこのアイドル歌手の人気がすごいのであれば10万円で売れる訳であって、コアなファンの買い占めが起こるだけです。
米だって同じことで(注1)、値段が高くても誰もがその値段で買うってことであれば、それは人気のあるアイドル歌手な訳ですから、業者からすれば値段を落として売る経済合理性がありません。備蓄米が放出されたとしても、流通業者にとっては高く売れるものを別ルートから安く手に入れたと言うだけの話で、一番高く売れる値段で売るに決まってますよね。となると儲かってるのは流通業者だよねって話で、一体全体政府は何を考えているのやら。なんだか利権の匂いがしません?
噂によると、米価高騰への対策としてふるさと納税制度を利用して米を手に入れると言う方が爆発的に増えたんだそうで、市町村によっては処理能力を超えた申し込みがあって、受け付けたは良いものの払い出す米がないと言うお粗末なことも起きているようです。私はふるさと納税制度ができて以来ずっとこの制度を利用して米を手に入れていたので、大丈夫かなーと心配していましたが、先月末に申し込んだ米が先日無事届いてホッとしました。
いつもお願いしているのは茨城県の米です。茨城県は亡父の故郷で、子供の頃は毎年盆暮れには訪れた思い出の地です。
この茨城県。「いばらぎ」と発音されがちですが、本来は「いばら『き』」で、由来は常陸国風土記に記載されている古いエピソードなんだそうです。いばら(茨)とは薔薇のように棘のある草木のこと、き(城)はお城の古い呼び方で、大昔にこの地域に赴任した執政官が茨で柵をつくって野盗から民を守ったと言う言い伝えから、「茨の城」すなわち「茨城」となったようです。明治期の人たちの豊かな教養を思い起こさせてとても好きな地名です。
今となっては祖父・祖母も父も亡くなり、すっかり疎遠になってしまいましたが、毎日毎日茨城県のお米にエネルギーをもらっている次第です。
しかし米の値段。
誰もがこの値段でも買うのであれば元々の価格が低すぎたとも言えますから高いのは仕方がないとしても、流通業者ではなく農家さんに還元されるように政策的になんとかならないもんですかねぇ。やっぱり利権がらみなんですかねぇ。
♪備蓄米 誰の懐 満たしけん 濡れ手に米や 見えざるその手
(大伴ヤキモチ)
注1)米の場合はアイドル歌手のような希少性はないので、米が巷に溢れて掃いて捨てるほどになったってことなら値段は下がるとは思いますが。

茨城県産コシヒカリ(^^)